公共交通機関の「優先席」をめぐっては、度々、「(ある属性に)譲るのがマナーだろう」という、いわゆる「マナー警察」問題が持ち上がります。
座っている側にも、見た目には判らないが「席を必要とする理由」がちゃんとあり、にもかかわらず、不毛の争いが起きることがしばしば。
(「子ども連れ」「障害を持つ人」「病気の人」「ケガしている人」「高齢者」「妊婦さん」「疲れている人」…等々、様々な理由がありますよね)
今回は、この「優先席の“取り合い”」問題、いかに解決できるか、考えてみたいと思います!
「優先席」をめぐる争いと、問題点
「優先席を安全な場に」という問題提起
今回は、とある朝日新聞の「声欄」への投稿がきっかけでした。
SNSでは、様々な声が上がります。
今日の朝刊にワテの体験が載ったのでフォロワーさんに見てほしい。#知的障害 pic.twitter.com/EuDKYds3Lg
— ヤモリ夫人 (@yokohama_ids) September 26, 2025
ある日、この投稿者さんが、お子さん2人と一緒に 電車の優先席に座っていたところ、のり“老夫婦”より「最近の若者は席を譲らない」と嫌味を言われたのだそう。
お子さんは、立っているのが困難なため、この方はお子さんのために「勇気を出して」譲らなかった、といいます。
見た目では判らなくても、優先席を必要とする人がいることを知ってほしい、
安心して座れる優先席であってほしい、とうったえます。
Xの声は「自分の経験に基づいた声」が多かった
Xの声で1番多かったのは、皆さん、ご自身の経験上で、「どの属性の人」が「譲ってくれる(くれない)か」という話題でした。
「“若い人”は譲ってくれない」、逆に「“若い人”は、譲ってくれる」、
「“男の人”は、譲ってくれない」、逆に「“男の人”は譲ってくれる」。
また、この投稿主と同じ経験(“高齢者”の乗客から圧をかけられた)をした人から、共感の声が集まっていました。
しかし、同時に“高齢者”をひとくくりにして非難する声も、少なからず見かけました。

こういう時、
嫌な思いをした人も、譲ってもらって助かったという人も、
「属性や年齢」に結びつける語りが発生しがちなのですが、
全く逆の意見が出現していることからも、相関性はありません。
また、“若い人は”という表現に反応して、「仕事帰りで疲れ切った30代は許して」という、切実な声も。



もちろん、仕事で疲れている人も含めて、
「優先席」は、必要とする人が誰でも座っていいのです。
誰でも利用できる「優先席」
しかし、声欄の投稿主さんは、「優先席、誰が優先?」という事を議題にしたいわけではなく、ましてや皆が「特定の属性」を非難したりすることは望んでいません。
主さんの願いは、声欄の投稿にある通り「安心して利用できる優先席にしたい」という問題提起です。
当然のことですが、「優先席」に座るための「優先順位」があるわけではありません。
妊婦さん、お子さん連れ、「障害」をお持ちの方(ヘルプマークで判断できるケース)、「ご高齢」の方、ケガをしている方など、見た目で判るケースでは、自分が元気である時に「譲る」方は多いでしょう。
しかし、先ほどの「仕事で疲れている」等、見た目で判らないケースは、たくさんあります。
妊娠初期の妊婦さん、「障害」をお持ちの方(見た目には判らないケース)、持病がある方、疲れている・具合が悪い方(老若男女問わず!)などなど。
「ヘルプマークを付けたら良いのでは?」の声
驚いたのは、「ヘルプマークを付けさせればいいじゃないか」と、主さんや、主さんのお子さんを責める声が、複数見られたことでした。
もちろんのこと、障害や病気を、開示する必要はありません。
主さんも、声欄の中で「持病を明かしたくない人もいるでしょう」と、書いて下さっている通り、
非常にデリケートなことであり、そもそも「個人情報」です。
これを他人が「開示せよ」、あるいは「受容せよ」というのは、きわめて暴力的な、強要なのです。
2013年施行の「障害者総合支援法」には、「意思決定支援」が明記されました。
これは、障害のある人が、自分の意志で物事を決めることを支援することです。
支援者・保護者が代わりに決めるのではなく、本人の希望・意向を尊重します。
「障害者の権利に関する条約」(2006年に国連で採択された条約。日本は2014年に批准)の中でも
「すべての障害者が他の者と平等に、法の下の人格を認められること」
「意思決定において、必要な支援を受ける権利を有すること」
が定められています。



そもそも、障害があっても無くても、(当たり前ですが)優先席は利用出来ます!
「席を譲られて困る」ケースもある
主さんの投稿から派生し、様々な声が出るなかで、「席を譲る」ことについて、こんな意見も見られました。
それは、「席を譲る」ことで “高齢者”の方の心を傷付けてしまう、というもの。
これも、とてもデリケートな問題です。
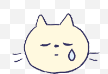
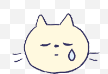
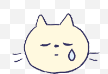
もちろん、譲ってもらって嬉しい方もいますが、
「席を譲ろうと思うほど、私は年老いて見えるのだろうか」と、傷ついてしまわれる方もいます。
また、腰痛がある人の場合、譲ってもらうのは嬉しいけれど、降りる時に立つ動作をすることが大変だったり、席から出口まで歩くよりも、出口近くに立っていた方が良い、という人もいます。
赤ちゃんを抱っこしている人に譲ると、もちろん大抵は喜んでもらえます。
しかし、まれに、赤ちゃんには「この高さがいい」(パパ/ママが立っている高さ)という時がありますから、断られる場合もあるでしょう。
「優先席」問題の解決方法を考える
解決方法は?シンプルに…
それでは、この「優先席問題」、どうやって解決するのが良いでしょうか?
それは、非常にシンプルなことですが、譲る方も譲られる方も、「聞いてみる」ことだと思います。
よく「思いやり」といいますが、
自分以外の、ひとの心は、自分には解りません。
想像を試みることはできますが、自分の想像と違う場合があるのは、当たり前のことですものね。
「すぐに降りられますか?もし良かったら、どうぞ」
「赤ちゃんご機嫌ですね。お母さん座っても大丈夫ですかね?」
このように、相手の方が「譲ってもらいやすく、かつ断りやすい」聞き方もあります。
これにも例外がありますよね。
前述の例にあったように、“ご高齢”の(と思われる)方に聞いたら、その方を傷付けてしまうかもしれません。
明らかに、立っているのが辛そう、と判る場合はもちろん声をかけます。
しかし、判断がつかない場合、筆者は、黙って席を立つようにしています。
そして、1番良いのは、
もし自分自身が辛いときは、「すみません、具合が悪いのですが、どなたか、席を代わっていただけますか?」と聞きやすい環境づくり。これが、文化として根付くことが、大切だと思います。
今はまだ、「なかなか、聞きづらい」という方、我慢してしまう方は、多いと思います。
声欄のケースのように、「若そうに見える人」をターゲットにして 席を立たせようとする行為に対して、毅然と言い返すのも、とても勇気が要る状況でもあります。
ゆくゆくは、気軽に安心して聞き合えるシステムを創ることが重要ですが、
それまでは、周りの人が、そういった行為から守る── 私たちが、乗り合わせた車内で声を掛け合うのが、大切ですよね。
世界のシステムを参考にしてみる・対話し続ける
世界各国で、「優先席」の取り組みは見られます。
これをヒントに、日本でも試してみる、そして、この課題について色んな人と対話し続けていく、これが大事なのだと思います。


“Please offer me a seat(席を譲ってください)” バッジ
日本にも、「ヘルプマーク」や「マタニティマーク」はありますが、「障害、病気、妊娠」以外でも、椅子が必要な人はいますよね。
“Please offer me a seat” バッジのシステムは、イギリス(ロンドン)の取り組み例です。
見た目で状況がわからない人でも、誰でも「自分が座る必要がある」という意思を他人に示せる、というのが、良いですよね。
2016年、目に見えない障害を持つ1,200人が、6週間 “Please offer me a seat” バッジを着用するトライアル試験に参加し、そのうち
- 72%の人が「バッジのおかげで楽になった」
- 86%の人が「席をお願いする自信が持てるようになった」
- 98%の人が「バッジを必要とする人に勧める」
と回答しています。(参考:TRANSPORT FOR LONDONプレスリリース 2016.12.22 )



ただ、課題はあります。
日本の「ヘルプマーク」の問題と同じで、
「座る必要があること」を表明したくない人にとっては、このシステムは利用できません。
その「表明したくない」と思ってしまう原因は、社会の側にあります。
「表明することが恥ずかしくなく、譲り譲られることが当たり前」な社会を作ることと、バッジの取り組みは、両輪で進めなければなりませんね。



また、マーク自体の周知も必要ですよね。
筆者は、マタニティマークやヘルプマークを付けていても、それによって席を譲ってもらった経験は0です。
しかし一方で、妊娠後期(お腹が目立つので)、乳幼児を連れている時には、助けてもらったり譲ってもらったりしました。
知ってもらうための啓発活動は、重要ですよね。
このロンドンの取り組みにおいても、毎年「Priority Seating Week」を設定し、ポスター広告、放送、駅構内ブースなどで、バッジの存在を周知するキャンペーンを行っています。
“Please offer me a seat” バッジは、2017年~2025年現在までで、15万2,000枚以上発行されました。
(当初はロンドンと南東部の住所にしか送れなかったのですが)2024年から、英国内のどの住所にもバッジを送れるようになっています。
「ルールにする」ことの弊害について
国・地域によっては、場合によっては「譲らなかった場合の罰則」がある地域もあります。
ただし、このような「ルール化・義務化」そして「罰則」は、譲らない人を非難する風潮が、より強まるだけだと予測されます。



「義務」ではなく、皆が心地よく利用できるシステムを、「皆で」創るのが良いですよね!
引き続き、当サイトでも、取り上げていきたいと思います。
世界各国の取り組みで、良い例があれば、また追記していきます!
コメント