万引き犯への「懲罰」と「抑止力」のために、顔画像をネットに晒すー。
これは今までも、度々問題になってきたことですが、あらためて、検証したいと思います。
そして、顔画像をあげた店は、名誉棄損など、犯罪に問われるのか、解説したいと思います。

記事の内容につきましては、記事作成時(2025年5月14日)時点の法律に基づいております。
法律は今後、改訂される場合もあることを、ご了承ください。
経緯と画像について
あるトレーディングカード専門店がXに、防犯カメラの万引きの映像をUPし、それが拡散されています。(2025年5月14日現在)
そのポストには、画像、そして「防犯カメラに顔が映っている」ことと共に、「明日の閉店までに支払いをして頂けない場合は被害届を提出します」という内容が書かれていました。
その翌日、同じ店のXで、その人たちが来店したこと、「これから捕まえる」というポストがあり、またその30分後に「警察に通報しました」「あまりにも悪質なので、被害届も出そうと思います」というポストがあがっています。(2025年5月14日現在)
拡散されたのは、どんな写真だったのか
ポストを見ると、顔画像は、顔の一部のみに「一応」ボカシを入れたというもので、背格好、着ている服や靴、背負っているバッグ、髪型など、全て本人たちを特定できるものです。
後ろ姿は、全くボカシが入っていませんでした。
複数の画像の中には、万引きの瞬間の画像も入っています。
この画像が入ったポストには、14万もの「イイね」が付き、2.9万リポストされています。
筆者の家から遠く離れたローカルなショップのポストにもかかわらず、筆者の目にも入ってきました。
驚くことには、まだ小学生か中学生と判る写真だったのです。
「犯人」の「顔画像を晒す」「SNSで叩く」は「抑止力」なのか?
それでは、「犯人」の「顔画像を晒す」、「SNSで叩く」行為について、見ていきます。
「顔画像を晒す」は、肖像権(プライバシー権)侵害・名誉毀損にあたる
結論を先に述べますと、もちろん、犯人であれ、先ず「顔画像を晒す」はやってはならないことです。
無許可で顔の画像を公開することは、肖像権(プライバシー権)侵害や名誉毀損に当たります。
自分で撮影したものではない写真であっても、その写真を無断で公開する行為は、肖像権侵害のおそれがあります。
肖像権侵害の基準は、以下の通りです。
- その写真から、個人が特定可能かどうか
- 拡散性が高いかどうか
- 撮影場所
- 撮影、公開許可の有無
1つずつ、見ていきたいと思います。
①の「特定可能か」については、「一応」ボカシを付けたことで、侵害にあたらない、と考えたかもしれませんが、背格好や服装で、特定されてしまう・知り合いが見ると、すぐに判るレベルです。
これは「特定できる」可能性が限りなく高いケースといえます。
②「拡散性」これは、間違いなく高いといえます。
SNSは、残念ながら、人の「憎悪の感情」に引っ張られる場所です。
それは有名な人へだけではなく、いち市民へも向けられ、その「袋叩き」の状態を目にしたことがある人は少なくないのではないでしょうか。
そこへ、このポストをあげれば、万引きをした子どもたちがSNSユーザーによって「袋叩き」になることは、予想がつくことと推察されます。
「明日の閉店までに支払いを」と、一見、温情のような文章を掲載していますが、特定可能とおもしき顔写真、窃盗の現場写真を掲載している時点で、犯人への憎悪を感じます。
お怒りの感情は理解できますが、明らかに一線を越えています。
③防犯カメラ映像ですが、提供して良いのは警察だけです。
SNSにアップすることは、肖像権侵害にあたります。
④について。防犯カメラの映像については、自治体ごとに厳しいガイドラインがあります。
防犯カメラの映像を取り扱う企業は、映像の流出や無断利用、紛失等が起きないよう、責任を持って映像を保管することが定められています。
実際に、そのお店がある自治体の「公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」を見てみると、
・画像の取扱いについて、防犯カメラの画像を、みだりに他に漏らしたりしてはいけない(秘密保持)
・設置者は、当該防犯カメラの設置・利用に関する苦情や問い合わせを受けたときは、適切かつ迅速な対応をする
と規定されています。
Xでも、「警察へ連絡してください。写真を削除してください。」「万引きは犯罪だが、私刑はダメです」とXユーザーから店への依頼が見られました。
しかし、お店は「警察に連行されました」とポストした後もなお、画像を掲載した当該ポストを削除しませんでした。
こちらに関しては、ガイドラインに抵触している可能性が高いです。
それから念のためですが、防犯カメラでの撮影自体が、肖像権の侵害になるケースは少ないです。
しかし、撮影した映像を、インターネットや店頭に公開すると、肖像権の侵害や、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
また、万引き犯の顔写真を公開してしまうと、その社会的評価が低下したとして、名誉棄損罪(刑法第230条第1項、法定刑は3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金)が成立したり、不法行為に基づく損害賠償のリスクも考えられます。
(引用元:小林裕彦法律事務所 コラムより)
自力救済の禁止
「名誉棄損」とはまた、別の観点からのお話です。
犯人の顔写真を公開すると告知して、商品を取り返そうとするのは「自力救済の禁止」に該当する可能性があります。
過去にも、漫画やフィギュアを取り扱う店が おもちゃを万引きされ、店側が「返品しなければ、防犯カメラの画像をホームページで公開する」と警告し、それが問題になったことがあります。
その時は、警視庁が店へ、顔画像の公開を止めるよう要請し、店が画像を公開することはありませんでした。
「自力救済の禁止」とは、権利を侵害された場合、法律の手続きによらずに、自らの手で権利を回復することをしてはならない、という原則です。
(これは、「万引き」等の犯罪に限らず、債権回収などにも適用されます。)
あくまでも、法律にしたがって、進める必要があります。
【なぜ、「自立救済」が禁止されているのか?】
「自立救済」を認めると、今回のように、名誉棄損に該当する行動を引き起こすケースが出かねない、そしてその可能性が高い、ということが分かります。
「自立救済」が、名誉棄損や脅迫罪など、さらなる犯罪を誘発しかねません。
このことから、社会秩序を保つため、日本をはじめ多くの国で「自立救済」は原則として禁止されています。
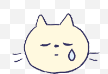
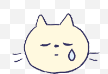
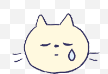
自分の自転車を盗もうとしている人から直接、その場で自転車を取り返すことは、「自力救済にはあたらない」とされる可能性が高いのですが、あくまで「限定的に認められる」場合です。
その際に、犯人が暴力をふるってくるなど、自分が危険にさらされる場合もあります。
「誹謗中傷」は「抑止力」なのか?
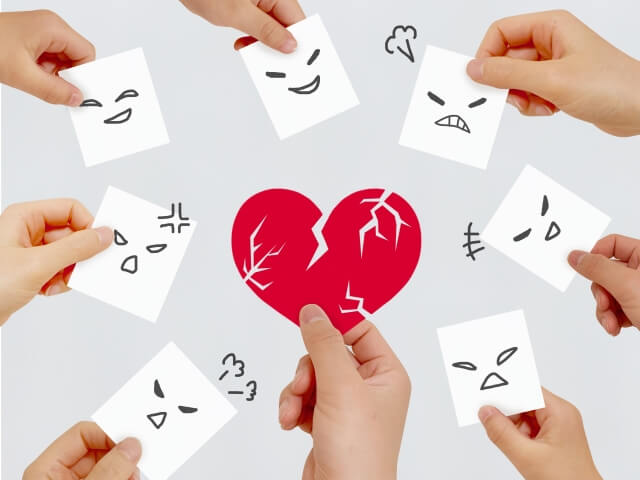
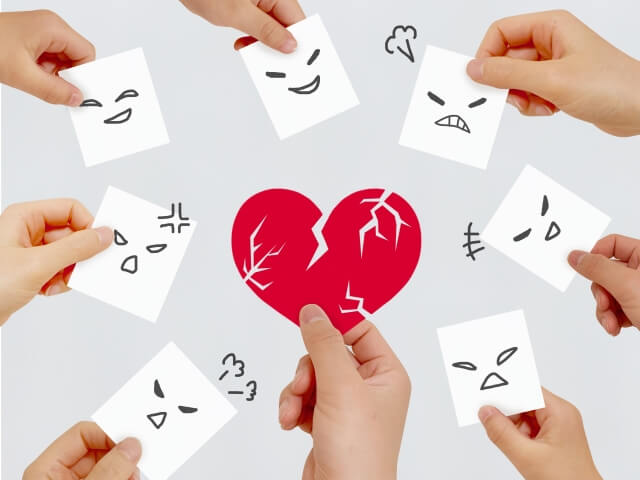
また、「画像を晒す」にとどまらず、SNSでは 多くのユーザーが(ー中には、店の行為を止めようとするポストも複数見られましたがー)、「憎悪」に引きずられ、「万引き犯」に対して誹謗中傷を行っているのを、筆者も目撃しました。
(筆者も止めようとした1人ですが、憎悪は「止めようとしたユーザー」の人々へも向けられ、誹謗中傷が飛びかっていました。)
このように、Xで吊るしあげることー「誹謗中傷」は、もちろん やってはならないことで、犯罪です。
犯罪は法律によって裁かれるもので、ユーザーのするべきは、「どうしたら万引きが起きないようにできるか」皆で考えることに尽きます。
「万引き」は、窃盗であり、犯罪です。
そして、誹謗中傷も、犯罪なのです。
誹謗中傷は、刑法230条1項での「名誉毀損罪」、民法709条での「不法行為」に該当する可能性があります。
(参考:弁護士法人 心 町田法律事務所 )
肖像権の侵害に対する「刑事上」の罰則は基本的にありませんが、SNSなどでの肖像権侵害の場合は「名誉毀損罪」に該当する可能性があります。
また、「刑事上」の罰則が無い場合においても、「民事上」の責任を問われる場合があります。(損害賠償請求・差止請求など)
(参考:Authense コラム/はばたき法律事務所 )



今回の、「犯人」への「ネットでの誹謗中傷」は、人間の「処罰感情」から来ています。(冷静な指摘と、誹謗中傷は、異なるものです。)
憎悪に引きずられそうになったら、「あ、いま“処罰感情”がはたらいているな」と気付くことが大切です。
もし、そういう感情になったら、SNSに投稿をせず、自分の気持ちと向き合いながら落ち着きを取り戻しましょう。
人間の脳には「ドーパミンニューロン」という神経細胞があります。
ここの報酬系回路には、様々なものがありますが、「悪い事をした人」に「罰を与える」というのもまた、人間の「報酬系回路」を活性化させるということが分かっています。
(参考:『〈叱る依存〉がとまらない』村中直人さん著 46~50頁)
例えば、芸能人同士の恋について、自分たちの生活に何ら関係を及ぼさないのに、SNSで「誹謗中傷」が起きていますよね。この現象は、人間が「処罰感情の充足」により脳の「報酬」を得たいから起こります。
こういった行動は「手放す」ことが可能です。
「厳罰」は「抑止力」なのか
筆者は、このケースが「未成年者に対して」であったことに1番 驚きました。
大人に対しても、もちろんのこと、肖像権侵害や誹謗中傷はやってはならないことです。
しかし、大人の万引き犯ではなく、子どもの万引き犯を「見せしめ」に吊るしあげたところが、「弱い者なら攻撃してもいい」という、2重に恐ろしい構造と感じます。
もちろん、成年者、未成年者にかかわらず「万引き」(窃盗)は犯罪です。
店は、SNSにアップするのではなく、警察に連絡するべきでした。
「厳罰化」は「抑止力」になるのか
前述の通り、万引きしている本人の画像をSNSにあげたり、「万引き犯」に対して誹謗中傷を行う行為はやってはならないことです。
しかし、SNSの中に「抑止力になるのではないか」という書き込みを多く目にしました。(誹謗中傷の投稿ではなく、純粋に意見として書き込んだ人々が一定数、見受けられました)
もちろん「SNSで晒す」ことはNGですので、ここでは(誹謗中傷ではなく、法律の下での)「厳罰化」と、考えてみましょう。
果たして「厳罰」は、「抑止力」になるのでしょうか。


日本における「厳罰化」
一見、「厳罰」には「抑止力」が働いて、再犯を減らすのではないか、と思われがちなのではないでしょうか。
しかし、実際にはその逆、「厳罰化」は、逆効果をもたらすといわれています。
かえって再犯率を高めてしまうことに繋がってしまうのです。
日本では、2021年に少年法が改訂され、実際に「厳罰化」されています。
【「原則逆送府対象事件」とは?】
「家庭裁判所が逆送しなければならないとされている事件」のことです。
少年の事件については、先ずは必ず、すべての案件が家庭裁判所に送られます。
調査のうえで、「刑事処分が相当」と認められる事件については、検察官送致(これを「逆送」といいます)され、検察官が刑事処分をする、というものです。
新・少年法では、この「原則逆送府対象事件」の適用範囲が拡大されました。
それでは、この「厳罰化」は「抑止力」となったのでしょうか?
少年の刑法犯検挙人員の推移
それでは、刑法犯少年の検挙人員・人口比の推移を見てみましょう。
| 年次 | 触法少年(刑法)の補導人員(人) |
|---|---|
| 2014年 | 48,361人 |
| 2015年 | 38,921人 |
| 2016年 | 31,516人 |
| 2017年 | 26,797人 |
| 2018年 | 23,489人 |
| 2019年 | 19,914人 |
| 2020年 | 17,466人 |
| 2021年 | 14,818人 |
| 2022年 | 14,887人 |
| 2023年 | 18,949人 |
参考:警視庁HP 図表2-92 刑法犯少年の検挙人員・人口比の推移(平成6年~令和5年)より抜粋
人数の推移を見ると、2021年まで 減少の一途をたどっていた人数が、(新少年法が施行された)2022年から増加する傾向になっています。
このデータのみで一概には言えません。犯罪には、様々な要因、背景があるからです。
しかしながら、検挙人数が減っていない(やや増えている)ことが見て取れます。
「厳罰化」には「抑止力」の効果は、現時点では見られないことが分かります。
「厳罰化」の弊害とは? かえって再犯率を高めてしまう可能性も
また、少年法が議論される中で、「厳罰化」による弊害が指摘されているのは、次の通りです。
更生の機会の減少
改訂により、「特定少年」に対する保護処分の機会が減少し、更生支援に繋がることが難しくなる可能性が指摘されています。
実名報道の解禁による社会的制裁
前述の通り、起訴された場合「実名報道」されることになり、社会的制裁が強まっています。
これにより、更生の機会が奪われるという批判もあります。
刑の長期化
改訂により、特定少年に関して、懲役刑の可能性が拡大されました。
刑の長期化により、社会からの孤立を深めてしまい、再犯につながってしまうことが懸念されています。



では、少年犯罪を減らすには、どうすればいいのでしょうか?
少年犯罪検挙人数は、1990年代から大幅に減少している
少年犯罪の報道が増えたことにより、あたかも「少年犯罪が増加している」ように錯覚してしまうのですが、前述の通り、少年犯罪検挙人数は、減少しています。
先ほど、2022年から増加傾向にあることを解説しましたが、さかのぼってみると 1998年の検挙人員は157,385人であり、それ以降は(増加した年もありましたが)減少してきています。
2022、2023年が増加傾向、といっても、1998年ピーク時の検挙人数の8分の1です。
参考:警視庁HP 図表2-92 刑法犯少年の検挙人員・人口比の推移(平成6年~令和5年)
このような大幅な減少は「厳罰化」の成果ではありません。
ここまで減少することができた背景は、子どもたちを取り巻く社会環境の変化や、警察の再犯防止の取り組みなど、多岐にわたるでしょう。(若年層の人口自体が減少していることもあるのではないかと、言われています。)
しかし近年「わずかながら」増加傾向が見られることについて、多角的な分析と、対策が急がれます。
それが凶悪犯罪である場合には、被害者や被害者遺族にとって、社会にとって、決して「わずか」などではありませんから…
更生支援の重要性
再犯しないために必要なのは、更正するためのプログラムです。
少年犯罪の再犯防止には、教育、職業訓練、心理的なケア等、包括的な更生支援が必要です。
今回のように、窃盗であれば、クレプトマニアの治療が必要で、自助グループに繋げることも大切です。
「厳罰」ではなく、社会全体で更生支援体制を構築していくことこそが、再犯率を下げ、ひいては犯罪を無くしていく社会に繋がります。
被害者支援も重要
窃盗(万引き)に限らず、犯罪被害者は社会で支えていくことも大切です。
全国万引犯罪防止機構でも、対策のシェアや、ロス対策の学びなど、様々な活動が行われています。
「スーパーマーケットトレードショー2025」に万防機構のご紹介スペースを設けております。係の者もおりますので、是非、お気軽にお越しください。Hall5入口すぐです。#万防機構 #スーパーマーケットトレードショー #幕張メッセ pic.twitter.com/46vZ6uNVCo
— 全国万引犯罪防止機構 (@manboukikou) February 13, 2025
【#ロス対策】万防機構ホームページに、第12回ロス対策検定試験の過去問をアップしました。どんな試験かご興味のある方は、是非、ご確認ください。https://t.co/YPM2fY0AkO#万防機構 #ロス対策士
— 全国万引犯罪防止機構 (@manboukikou) January 23, 2025
コメント